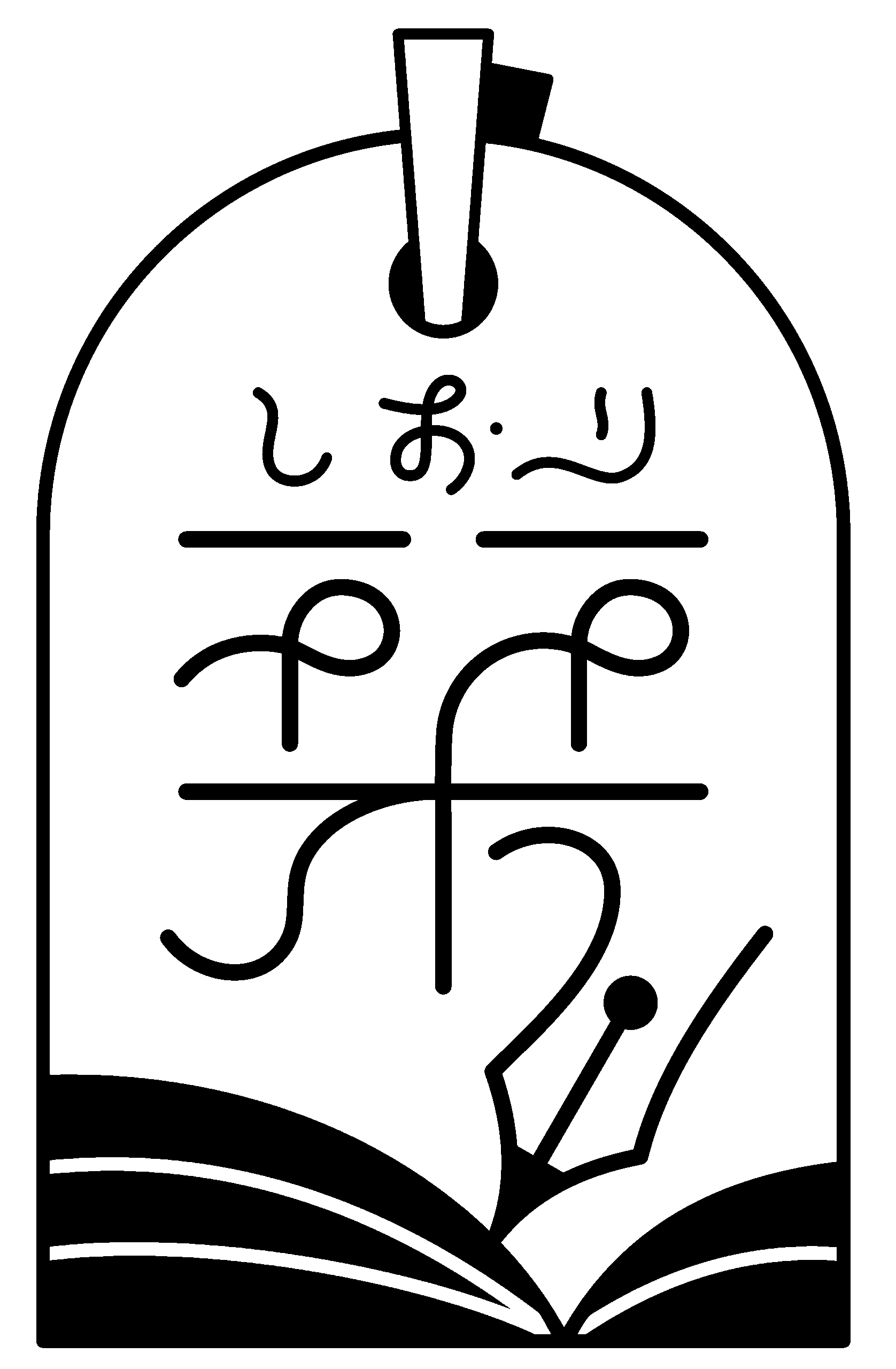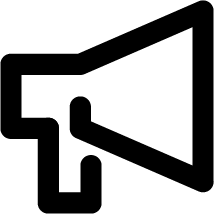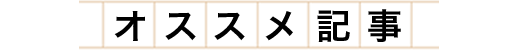「、」「。」
「あけましておめでとうございます」って、いつまで言っていいんだ?
この一週間、仕事始めに追われながら
新年のご挨拶ネタの期限いつまで許される問題に焦っていました。
調べてみた。
暦の上では、元旦(1月1日)が大正月で”松の内”までが小正月。
”松の内”とは、門松などのお飾りを飾っておく期間で
関東では1月7日、関西では1月15日まで。
大正月から小正月までがお正月の挨拶、「あけましておめでとう」を使うに適した期間とのこと。
……(本日1月13日)。
弊社は関東にございますが、
これをご覧になる方々は全国世界ワールドワイドということで
あけましておめでとうございます
新年快樂
새해 복 많이 받으세요
สวัสดีปีใหม่
Feliz año nuevo
Bonne année
Buon Anno
Frohes Neues Jahr
Happy new year
…
本年もどうぞよろしくお願いいたします!
世界各国いろんな伝統文化があることでしょう。
何となく過ごしている年中行事。改めて仕来りを調べてみると面白い。
日本の例えば、年賀状に句読点を使ってはいけません。
理由は二つ。
(1)祝い事に区切りをつけてしまう。良いことがずっと続いてほしい験担ぎの意味が込められている。
(2)相手に敬意を表すため。 「句読点をつけないと文章が読めない人」と相手を見下すような意味合いが含まれてしまう。
(2)の意味どういうこと!? 「句読点を使うと相手を馬鹿にしてる?」そんな馬鹿なです。
調べてみた。
どうやら句読点が普及したのは明治時代。
日本には遥か昔から江戸時代まで、墨と筆を用いて文書を書く文化があり、
毛筆の文化で「、」「。」で文章を区切ることはなかったそう。
それが明治時代、活版印刷が盛んになり、
印刷した新聞や小説などの文章で、句読点がないと文章が読みづらいことから用いられるようになる。
また、明治時代になり身分制度が廃止されて、
国民すべての人が就学することが公的に定めれた。
そこでどんな人にも読みやすいように、
ピクトグラム的な発想で(ここで文章を区切ると分かりやすいと)使うようになったのではなかろうか。
明治当時の知識階級・伝統文化を大切にする人たちにとって、
「、」「。」は、新興で馴染みのない浅いものだったのだろう。
だから(2)の理由があったというわけ。
※上記は個人による見解です。寄せ集めの知識のため間違えがありましたら申し訳ございません。
時代を経ると、意味がわからない年中行事や文化。
なんでそうなったのか知ると面白い。
ちなみに年賀状も松の内までが適した期限。
松の内を過ぎてから出す場合は「寒中見舞い」がよいでしょう。